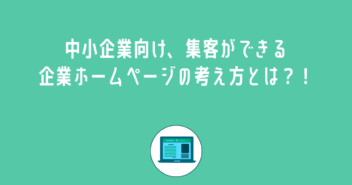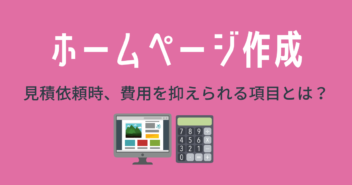病院やクリニックなどの医療のホームページ制作における成功の7つのポイント
多くの集患が上手くいっていない病院のホームページは、残念ながら「患者さんが何を知りたいか」という視点が欠けており、ただ存在するだけのものになりがちです。
患者さんの不安に寄り添い、信頼を得て「この病院に行きたい」と思ってもらうためには、戦略的なウェブサイト設計が不可欠です。
ここでは、成果を出すために押さえるべき重要なポイントを、具体的な施策と共に詳しく解説します。
目次
1.目的を明確化する
まず、「誰に」「何を伝え」「どう行動してほしいか」というウェブサイトの目的を具体的に設定します。目的が曖昧だと、デザインやコンテンツの軸がぶれてしまいます。
新患の来院を増やすのか?
- どんな症状の患者さんに来てほしいのか?
- 医院の強みや特徴を前面に出し、初診の方向けの丁寧な案内やWeb予約システムが重要になります。
再来院の患者さん向けの情報発信か?
- 診療時間の変更、新しい治療法の導入、季節性の疾患に関する注意喚起など、リピーター向けのコンテンツを充実させます。
地域の患者さんに認知してもらいたいのか?
- 地域名を含んだSEO対策や、地域医療への貢献などをアピールします。
遠方の患者さんにも来てほしいのか?
- 専門性の高い治療や独自の手術など、その医院でしか受けられない医療を詳細に解説し、オンライン診療や遠方向けのアクセス案内も有効です。
採用活動を強化したいのか?
- 採用ページを設け、職場の雰囲気や理念、スタッフインタビューなどを掲載します。
2.ユーザー(患者)が本当に知りたい情報を網羅する
患者さんは不安を抱えながら情報を探しています。ただ情報を羅列するのではなく、「知りたいであろう情報」を先回りして提供することで、安心感と信頼感が生まれます。
必須の基本情報
診療時間、休診日、住所、電話番号、アクセス(地図、最寄り駅からの道順、駐車場の有無)
信頼性を高める情報
医師の紹介: 院長の挨拶だけでなく、経歴、専門資格、所属学会、治療に対する考え方など、人柄や専門性が伝わる詳しいプロフィール。
医院の理念・診療方針: どのような想いで患者さんと向き合っているかを伝えます。
院内の様子: 受付、待合室、診察室、医療機器などの写真を豊富に掲載し、清潔感や雰囲気を伝えます。
具体的な診療内容
対応可能な診療科目・症状: 「内科」だけでなく「風邪、腹痛、生活習慣病(高血圧、糖尿病)、アレルギー」など、具体的な症状を記載すると検索に強くなります。
料金表: 保険診療・自費診療の料金を明記し、会計の不安を解消します。
得意な分野・専門性の高い治療内容
得意な治療・手術: 専門性の高い治療について、内容、流れ、費用、リスクなどを詳しく解説します。
※これらの詳細な情報をウェブサイトに掲載できるのは、後述する「広告可能事項の限定解除」の要件を満たしている場合に限られます。
3.患者の知りたい情報の優先順位をつけ、スマホファーストで設計する
今や、病院を探す人の8割以上がスマートフォンを利用しています。
PCサイトをスマホ対応させるのではなく、最初からスマートフォンでの見やすさ・使いやすさを最優先に設計(スマホファースト)することが必須です。
優先順位の付け方
「初めてサイトを訪れた、症状に悩む患者さん」が最も知りたい情報は何かを考え、それをトップページの上部に配置します。多くの場合、「診療科目」「受付時間」「アクセス」「電話番号」が最優先されます。
スマホでの使いやすさの工夫
- 電話番号はタップすればそのまま発信できるようにする。
- Web予約ボタンは、常に目立つ位置に固定表示させる(追従ボタン)。
- メニューはハンバーガーメニュー(三本線のアイコン)にまとめ、すっきりと見せる。
- 文字サイズやボタンの大きさは、指でタップしやすいサイズにする。
4.医院の「強み」を具体的に言語化・明確化する
「◯◯科」と書くだけでは、他の医院との違いは伝わりません。患者さんは「自分の症状を一番よく診てくれるのはどこか」を探しています。
強みの見つけ方
- 院長が最も得意とする治療や専門分野は何か?
- 導入している最新の医療機器は何か?
- 「痛みの少ない治療」「女性医師が在籍」「駅直結」「キッズスペース完備」など、他にはない特徴は何か?
伝え方の工夫
- トップページの最も目立つ場所(ファーストビュー)で、「〇〇市で腰痛治療に強い整形外科」「働く女性のための婦人科」のように、キャッチコピーで強みを明確に伝えます。(※注)
- 強みを裏付けるために、その分野に関する詳しい解説ページやブログ記事(コンテンツ)を作成し、専門性の高さを示します。
(※注) 「〇〇に強い」といった表現は、客観的な根拠(例:年間手術件数など)が示せない場合、「誇大広告」と見なされるリスクがあるため注意が必要です。客観的な事実に基づいた表現を心がけましょう。
5.コンバージョン(予約・来院)への導線を設計する
有益な情報が掲載されていても、最終的なゴールである「予約」や「問い合わせ」に繋がらなければ意味がありません。
ウェブサイトの閲覧者は平均2〜5ページ程度しか見ないと言われています。
具体的な導線設計の例
- 全てのページに、予約ボタンや電話番号へのリンクを分かりやすく設置する。
- 症状や治療法の解説ページを読んだ後に、自然と「診療予約はこちら」「ご相談ください」といったボタンが現れるように配置する。
- 患者さんが迷わないよう、サイト構造をシンプルにし、「今どこを見ているのか」が直感的に分かるデザインにします。
6.スマートフォン対応を徹底する
前述の通り、スマートフォン対応はもはや「やって当たり前」の時代です。
PCで見たときに綺麗でも、スマホで見ると文字が小さすぎたり、表示が崩れていたりするサイトは、患者さんの離脱を招き、信頼を失います。
チェックポイント
- 完成チェックは必ず自身やスタッフのスマートフォンで行う。
- 画像の読み込み速度は遅くないか?
- 地図アプリと連携し、タップ一つでルート案内が開始されるか?
- 入力フォームはスマホで入力しやすいか?
7.医院の強みを軸にSEO・MEO対策を行う
ウェブサイトは作って終わりではなく、知ってもらうための努力が必要です。
SEO対策 (検索エンジン最適化)
Googleなどの検索結果で上位に表示させるための対策です。
- キーワード選定: 「地域名 × 診療科目」(例: 新宿区 内科)、「地域名 × 症状」(例: 渋谷区 頭痛)といった、患者さんが実際に検索するであろうキーワードを意識して、サイト内の文章を作成します。
- 専門性の高いコンテンツ: 医院の強みである疾患や治療法について、専門的で分かりやすい解説記事を定期的に追加していくことは、非常に有効なSEO対策です。
- E-E-A-Tの意識: 医療情報は人の生命や健康に関わるため、Googleはサイトの「経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)」を非常に厳しく評価します。誰が監修・執筆した情報か(医師のプロフィール明記)、情報源は何かを明確にすることが不可欠です。
MEO対策 (マップエンジン最適化)
Googleマップでの検索結果を最適化する対策です。地域性が高いクリニックにとっては特に重要です。
- Googleビジネスプロフィールの充実: 無料で登録できるGoogleビジネスプロフィールに、正確な医院情報(診療時間、住所、電話番号)、院内外の写真、提供しているサービスなどを詳細に登録します。
- 口コミへの返信: 投稿された口コミには、丁寧かつ誠実に返信することで、患者さんとのコミュニケーションを大切にする姿勢が伝わります。
【重要】Webサイト制作で遵守すべき「医療広告ガイドライン」
病院のウェブサイトは「広告」と見なされるため、厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」を遵守する必要があります。違反すると罰則の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
「広告可能事項の限定解除」について
本来、医療広告で表示できる内容は厳しく制限されています。しかし、患者が自ら情報を求めてアクセスするウェブサイトについては、以下の4つの要件をすべて満たすことで、この制限が解除され、治療内容や医師の経歴など、より詳細な情報の掲載が可能になります。
- 患者が自ら情報を求めてアクセスするウェブサイトであること
- 問い合わせ先(電話番号、メールアドレス等)が明記されていること
- 自由診療について、通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間・回数が記載されていること
- 自由診療について、主なリスクや副作用が記載されていること
これらの要件を満たして初めて、専門性の高い治療内容などを詳しく解説できる、と理解することが重要です。
禁止されている表現の例
上記の「限定解除」の要件を満たしたウェブサイトであっても、以下の表現は引き続き絶対的に禁止されています。
- 虚偽広告: 内容が事実と異なる広告
- 例:「絶対安全な手術」「必ず治る」といった、医学的にあり得ない表現。
- 比較優良広告: 他の医療機関と比較して自院が優れていると示す広告。
- 例:「日本一」「No.1」「地域で最も選ばれている」など、たとえ客観的な事実であったとしても、最上級の表現は全面的に禁止されています。
- 誇大広告: 事実を不当に誇張し、患者に誤認を与えるおそれのある広告。
- 例:客観的な根拠なく「最先端の治療」と表現すること。
- 患者の体験談: 治療内容や効果に関する患者の主観的な感想や体験談の掲載は、形式を問わず全面的に禁止されています。
- 治療前後の写真(ビフォーアフター): 原則として掲載禁止。掲載するには、写真に隣接して、治療内容、標準的な費用、期間・回数、主なリスク、副作用などの詳細な説明を併記することが必須です。
- 品位を損なう広告: 医療の品位を損なう、過度な価格強調やキャンペーン告知。
- 例:「期間限定半額キャンペーン」「相談された方全員にプレゼント」など。